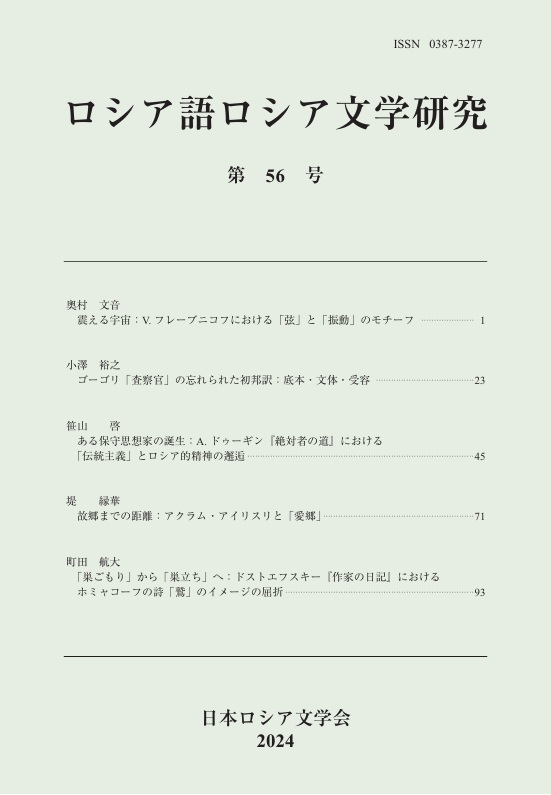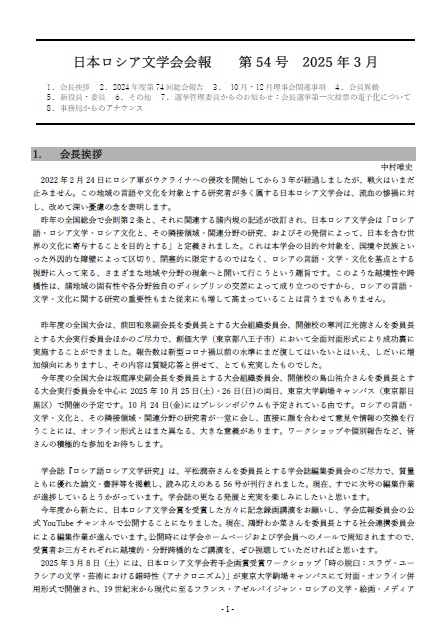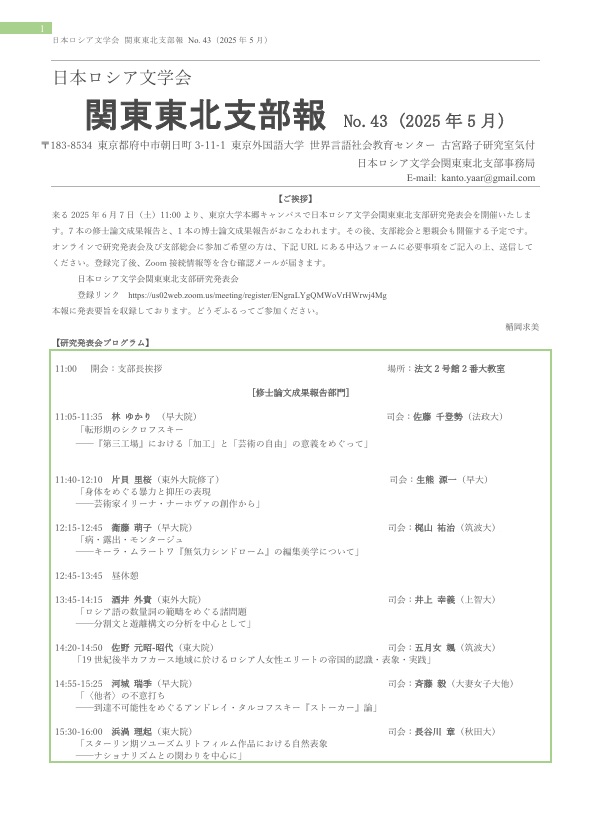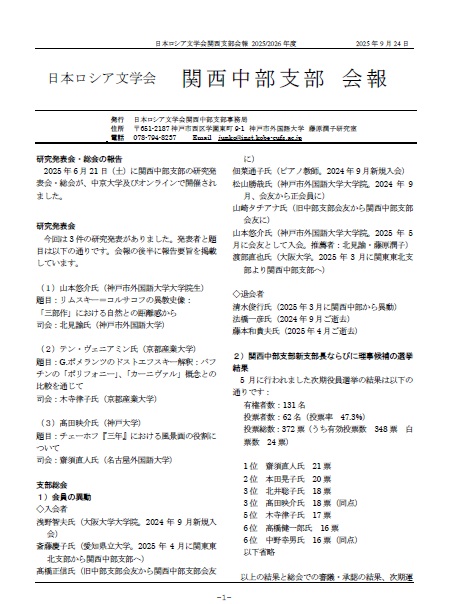野中進新会長 ご挨拶
会長就任にあたってのご挨拶
野中進
2025年11月
この度、日本ロシア文学会会長に選ばれました。歴史ある学会の長に選ばれたことは身に余る光栄ですが、戸惑いとプレッシャーも感じています。会員の皆さまのご支援を強くお願いいたします。
ロシア文学会は「ロシア語・ロシア文学・ロシア文化と、その隣接領域・関連分野の研究、およびその発信によって、日本を含む世界の文化の発展に寄与することを目的とする」(会則第2条)専門家集団です。本稿では、「学会」という社会的責任を負う形式で集団を形成することで何ができるのか、何をなすべきなのかについて考えてみたいと思います。まだ会長になったばかりなので、問いばかりで答えのない議論になるでしょうが、ご興味のある方はお付き合いください。
(1)若手研究者の支援と育成
最近、刊行された『Curricula Vitae-日本ロシア文学会75周年記念インタビュー集』を読んでも分かるように、ロシア文学会では設立当初から若手支援に力を入れてきました。私も1993年、初めて学会で報告した際、学会奨励賞というものをいただき(武田昭文さん、臼山利信さんと同時受賞でした)、大きな励ましとなったことを覚えています。ここ十年来では、学会参加補助、国際交流助成、学生会員、若手企画賞など、次々に新しい制度が作られてきました。また、日本学術振興会賞、育志賞など外部の権威ある賞への若手会員の推薦も積極的に行っています。この路線は今後もますます充実させていきたいと考えています。
その一方、大学・研究所などにおけるテニュア付き常勤ポストは減少の一途をたどっており(とりわけ人文系・外国語系で)、とくに若手・中堅研究者は非常勤や任期付きポストなどの雇用条件下で高い研究成果を要求されるという厳しい環境にいます。まだ若くして学会を去られる方のお名前を総会などで見聞きするにつけ、残念に思われる会員は多いでしょう。大学以外でもロシア文化と関わる途はあるはずで、そうした途に進む会員を学会として支援することはできないものかと思案します。大学と社会が交流する場として学会が機能するべきであり、そのためには様々な成功事例を積んでいきたいと考えています。
(2)社会への発信と責任
ロシア文学会では、大賞記念講演やプレシンポジウムを中心に、一般公開の企画を行ってきました。また近年では大賞・学会賞受賞者の記念講演のYou Tube配信も試みています(https://www.youtube.com/channel/UCnIsWlApaePrzXCQCAK8aLg)。今後も、故・三谷惠子元会長が創設された社会連携委員会を軸に、学会活動の社会発信を活発に行うべきでしょう。
社会への発信と責任と言えば、2022年以降、ウクライナ戦争に関する態度表明が個々の会員と学会全体にとって重い課題となっています。人文系の学会として過度に政治的な行動をとるつもりはありませんが、ロシアの言語文化に関する専門家集団としての社会的・倫理的責務は免れません。私としては、中村唯史前会長時代に発出された3文書――「ロシア軍のウクライナ侵攻への抗議声明」(https://yaar.jpn.org/?p=101)、「ロシアの言葉・文学・文化を今、あるいはこれから学ぶ皆さんへ」(https://yaar.jpn.org/?p=94)、「国際学術交流に関する執行部の見解」(https://yaar.jpn.org/?p=1345)――を踏襲したいと考えています。今後、状況に応じてこれらの見直しが必要かどうかについては、開かれた議論を待ちたいと思います。
ロシア語・ロシア文学・ロシア文化の研究・発信を謳う以上、会員の一人ひとりがロシアとの関係と距離を考える必要があり、それは各自の学問的営みに反映せざるを得ない。そのプロセスは自分自身との「内なる対話」にも他者との「外なる対話」にもなるでしょう。実際、今年の全国大会2日目のワークショップ「プーチン体制下におけるロシア文化」では現在のロシアへの態度をめぐって率直な議論が交わされました。あくまでも学問的枠組を重んじつつも、価値的議論に踏み込むことを恐れるべきでないと思われます。そうした議論を基に、社会への発言と責任もより具体的なものになっていくでしょう。
(3)研究の多角化と国際化
ウクライナ戦争の影響もあるのでしょうが、ここ数年、ウクライナ、ベラルーシを含めた東スラヴ文化圏のあり方と内なる多様性を意識した研究が増えているように思われます。この方向性は学問的に有効であり、発展してゆくことが期待されます。ロシアの言語文化と言っても、そのロシアとは何なのか、どこからどこまでがロシアかという議論を私たちは(そしてロシア人も)ずっとしてきたように思います。その意味で、「東スラヴ文化圏」という枠組を今一度意識し、その内なる共通性と差異、統合と分化の過程を学問的に検証することは、今後数年にわたってロシア文学会の重要なテーマとなるのでないでしょうか。
その意味でも重要なのが、学会の国際化です。ロシアやウクライナに行くことが困難な今、日本ロシア文学会が一つの国際的ハブとなり、東スラヴ、東アジア、欧米、その他の地域から研究者が訪れ、最新の研究成果を討論し、人的交流を深められる場を提供するということはけっして夢物語ではありません。事実、本学会の国際枠はコロナ禍や戦争を経てもなお続いており、海外からの参加者との学問的・人間的交流は続いています。ロシア語や英語の報告に対して質問をし、議論に持ち込む。また、懇親会で和やかに談笑する。こうしたことは、これから多くの国際会議に参加するであろう若手研究者にとってもよい経験の場になるでしょう。
困難な条件下でもつながろうとする個人のイニシアチヴを、学会としてサポートしたいと考えています。
(4)世代を越えた対話と協力
最近刊行された『Curricula Vitae-日本ロシア文学会75周年記念インタビュー集』はとても面白い本です。まだお読みでない方にはぜひご一読をお勧めします。座長の坂庭淳史さんを始め「日本ロシア文学会75周年記念事業ワーキンググループ」の皆さんにこの場を借りてお礼申し上げます。
このインタビュー集を読むと、たとえば1960年代のロシア研究というものが「ペレストロイカ世代」の私とは全く異なる意味とあり方をしていたことを実感します。先生方が、われわれにとって歴史的な人物や出来事と直接の関りをもっていたことを驚きとともに知りました。この感想はおそらく「ソ連解体期世代」や「プーチン台頭世代」、「ウクライナ戦争世代」の皆さんも各人各様に感じられたことでしょう。
しかし、ロシア語・ロシア文学・ロシア文化を知りたい、できることなら究めたいという情熱は世代に関わりなく継がれてきたのだという「懐かしさ」と「誇り」がないまぜになった読後感も持つことができました。
世代の違いはしばしば対話を難しくするバリアのようになってしまいます。しかし本来、世代間の経験と知見の差は豊かな対話の素材であるはずです。学会では「交流のバリアフリー」も大切にしていきたいと思います。
その意味でも、年に一度の全国大会や支部大会、そして懇親会は、学会だけが提供できる大切な場です。最新の研究成果を聴き、その場で議論できる研究発表会。旧交を温めたり、以前から話してみたかった人に声をかけられる休憩時間や懇親会。こうした場の価値はどれだけオンラインが普及しようとも、なくならないでしょう。学会として守っていくべきものの一つであると思われます。
ただその一方、そうした大会の組織・運営、あるいは成果発表の最高峰たる学会誌編集・発行、社会発信のための学会HP、合意形成のための理事会・総会、「下部構造」をつかさどる会計業務などは多くの会員の皆さんにお願いしています。学会は専門家集団ですが、会員のボランティアで成立する団体でもあります。とくに委員長や事務局は責任が重く、本務校の業務をやりくりしながら学会業務に取り組んでくださっています。
これまでお話してきたように、学会としてやるべきことは多いのですが、組織がボランティアで成立している以上、ただ仕事を増やせばよいというわけにはいきません。事務局・委員会業務の効率化も重要なアジェンダです。シニア世代、若手世代からも委員会への参加をお願いする機会が増えるかもしれませんが、ご協力をお願いいたします。学会の持続的発展のために世代間の対話と協力がますます必要になっています。
これから4年間、どうぞよろしくお願いいたします。
以上