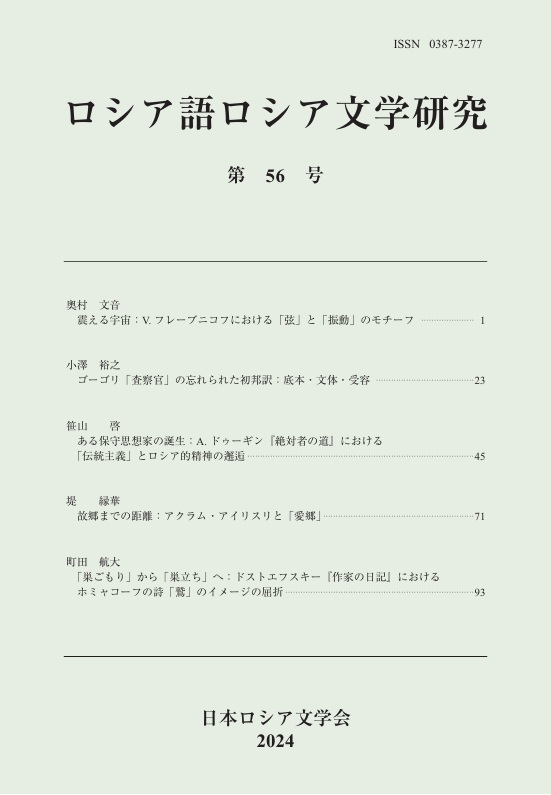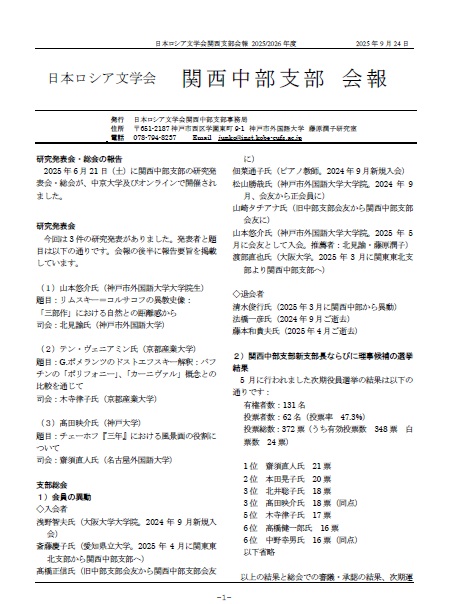追悼 法橋和彦先生
岩浅武久
2024年9月8日の夜、法橋先生が逝去された。91歳のご年齢だった。法橋先生と最初にお会いしたのは1963年に大阪外国語大学に入学した私が2年生になった時だから、先生はまだ31歳。長いお付き合いだった。大学で受けたトルストイやチェーホフについての講義は新鮮で刺激的だった。先生の研究室で定期的に研究会が開かれており、まだ学生だった私も、その研究会に参加していた。先生はその頃、ロシア文学のほか、文学批評の会編(稲垣達郎監修)の『現代文学研究叢書』(1966年)に「小宮山明敏試論」「資料、年譜」を書き、雑誌に太宰治についての論稿も書いておられた。
私は1967年に早稲田大学大学院に入学して、大阪外国語大学→早稲田大学大学院という、法橋先生と同じ道を辿ることになった。文学部読書室の書架に大学院卒業生の修士論文が配架されており、そこに法橋先生の論文もあった。修士論文の題名は『詩と詩人の使命 トルストイ研究序説』。『アンナ・カレーニナ』を中心に論じられていたが、その題名に法橋先生の研究者としての基本的な姿勢を見る思いがした。
日本文学の分野では、1969年に前述叢書に「小熊秀雄ノート――その民衆性の問題について」を書き、1972年には太宰治の「富嶽百景 論」を書かれたが、小熊秀雄に関しては、1972年に補説を加えた『小熊秀雄における詩と思想』(創映出版)を出版し、さらに2007年には、それらの論稿を含めた、いわば決定版の『暁の網にて天を掬ひし者よ――小熊秀雄の詩の世界――』(未知谷)を出版された。
専門のロシア文学ではトルストイを中心に研究を進められていたが、研究の主題はプーシキンやチェーホフにも及んだ。研究対象の変遷について法橋先生に訊ねたところ、「トルストイ研究を深めるためにプーシキンのことを調べている」という、先生独特の表現の答が返ってきたのを記憶している。もちろん法橋先生のプーシキン研究は「トルストイ研究を深めるため」だけでないことは、1999年に出版された『ロシア文学の眺め――プーシキン生誕二百年祭によせて』(新読書社)を読むとよくわかる。
法橋先生のお仕事で忘れてならないのは、「ロシア・ソヴェート文学研究会」を立ち上げ、ほぼ月1回の割合で定例研究会を継続されたこと。研究会には多くの研究者が参加し、会員たちの成果は会誌『むうざ 研究と資料』に発表された。『むうざ』誌は1983年3月の創刊準備号から今年(2024年)5月の34号まで発行された。法橋先生がトルストイ研究への思いをこめて2022年に出版された『さらば レフ・トルストイ』(未知谷)に掲載された論稿は、そのほとんどが『むうざ』誌に掲載されたものである。先生のトルストイ関連のお仕事で、2012年に上梓された『古典として読む『イワンの馬鹿』』(未知谷)はよく知られているだろうが、河出書房新社『愛蔵決定版 トルストイ全集』(1972~1978)の月報に連載された「日本におけるトルストイ(1)~(20)」は、広くは知られていないのではあるまいか。日本のトルストイ受容の歴史を克明に調査した貴重な労作で、先生の著書に収録されなかったのは残念でならない。
法橋先生が大阪外国語大学を退官された1998年に、畏友、澤田和彦、藻利佳彦の両氏と協力して『法橋和彦執筆目録――半生の控――』を作成した。そのとき初めて、法橋先生が1977年から79年にかけて、スポーツ紙に隔週連載された馬のエッセイがあることを知った。文学的競馬論とでも言うべきエッセイである。国会図書館で新聞を借り出してエッセイを読み、これは本にしたいと思ったが、それが実現したのは、ようやく一昨年(2022年)、扇千恵氏のご協力のもとに『月をみるケンタウルス――紳士の心得帳――』(未知谷)が出版された。90歳を前にした先生がお元気だったときに出版できたのは幸いだった。
法橋先生の文学研究は、詩と散文、空想と現実をめぐって展開されたというのは言い過ぎだろうか。今年の5月に発行された『むうざ』に法橋先生はプーシキンの詩をめぐる小論を書かれた。取り上げられているのは《Брожу ли я вдоль улиц шумных》から始まる無題の詩だが、法橋先生の翻訳に先生の読みがよく表れている。この詩にプーシキンの遺言詩を読み、その最終連の《И пусть [……] И равнодушная природа/Красою вечною сиять》を「静かに穂先をたれた小麦畑が 永遠の美で輝くもよし」と訳されている。「無関心な自然」に「静かに穂先をたれた小麦畑」を透視する先生の視線は、詩と散文、空想と現実の融合を願いつつ、その道を探求して止まなかった法橋先生の生き方そのもののように思われた。法橋先生のような方とめぐり合い、同時代に生きられたことは幸せだった。
法橋先生、有難うございました。近くまたお会いしましょう。