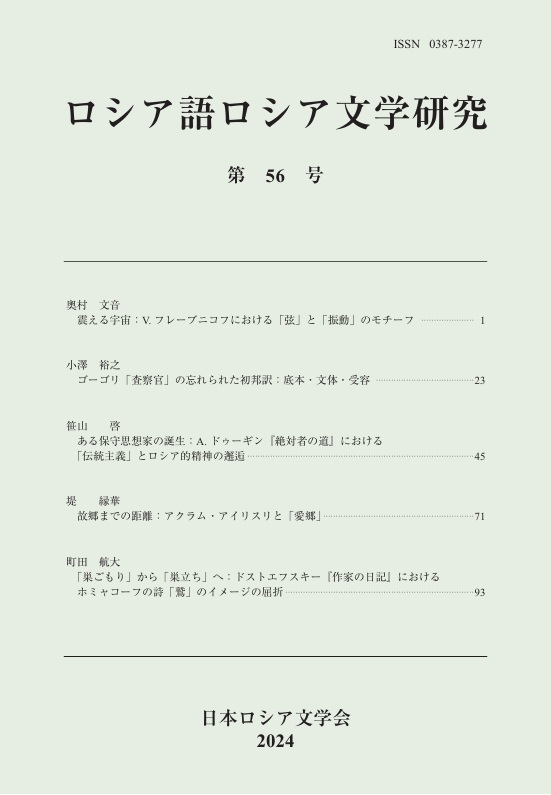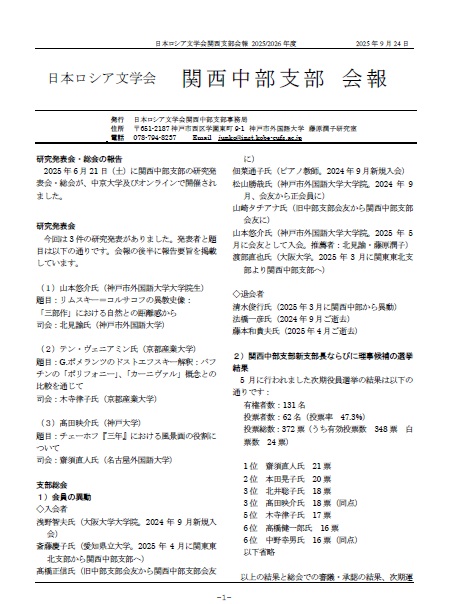2023年度 日本ロシア文学会大賞 受賞のことば
【受賞者】上田洋子氏(ロシア文学・演劇研究者、『ゲンロン』代表)
このたび、日本ロシア文学会大賞を受賞いたしました。まさかこのような賞をいただくことになるとは夢にも思っていなかったので、受賞のお知らせを伺ったときにはほんとうにびっくりしました。たいへん光栄で、また身の引き締まる思いです。心よりお礼申し上げます。
わたしは大学や研究機関に所属する研究者ではなく、株式会社ゲンロンという、思想家の東浩紀さんが創設した出版社の代表を務めています。今回の受賞では、個人としての研究だけでなく、ゲンロンが行っているロシア思想・文化などに関する発信を含めて評価していただきました。小さな出版社の在野の活動をこのような形で評価してくださる学会の懐の深さには、感謝の念に堪えません。
また、こうした活動は、多くのロシア文学会会員のご協力なしには成立し得ませんでした。とくに、2017年、批評誌『ゲンロン』でロシア現代思想特集を組んだ際には、監修者の乗松亨平さんをはじめとするみなさまのご尽力により、それまで日本語の情報がほとんどなかった愛国系の思想家・文化人の紹介など、社会的にも意味のある活動をすることができました。2022年のロシアによるウクライナ侵攻後に、ふたたびロシアの思想や文化、社会の現状についての小特集を組むことができたのも、ご協力くださったみなさまのおかげです。あらためて感謝を表したいと思います。
少し自己紹介をいたしますと、わたしはロシア文学と演劇、そしてアート・アクティヴィズムをおもな研究対象としてきました。博士号はシギズムンド・クルジジャノフスキー(1886-1950)という、キーウ出身で、モスクワで活動した作家の作品研究で取得しています。この作家はおもに1920年代から30年代にかけて執筆したのですが、社会風刺や西洋哲学へのオマージュがしばしば作品の根幹をなすせいか、生前はほとんど活字になりませんでした。しかし語りの名手だったおかげで人々の記憶に残り、国立文書館に保存された手稿をもとにペレストロイカ期に初めて本が出て、再評価が行われました。
わたしは大学院時代には研究に加え、演劇の分野を中心に通訳の仕事をしていました。装置や照明や音響とともに芝居が舞台に立ち上がっていくさまを何度も見て、演劇の裏側にあるさまざまな仕組みを学びました。その後、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館で研究助手の職につきますが、そこでは資料整理や展示などを通してものとその記憶・記録を扱い、テクスト中心の文学研究とは異なる研究のありかたに触れました。そんなわけで、大学院生時代からいまに至るまで、研究と現場の両方に軸足を置いた活動を続けてきました。
2012年、字幕監修を行ったアレクサンドル・ソクーロフ監督のドキュメンタリー『ソルジェニーツィンとの対話』の上映会が渋谷で行われ、かつて「ソルジェニーツィン試論」でデビューした東浩紀さんとの短い対談をすることになります。これがわたしとゲンロンの出会いです。ちょうど前年に助手の任期を終えたものの次の就職が決まっておらず、仕事を探していたときでした。
このとき東さんは東日本大震災後の復興を考えるために、「福島第一原発観光地化計画」というプロジェクトを始めていて、その一環としてチョルノービリ(チェルノブイリ)の取材を計画していました。当時、サッカーの世界大会「ユーロ2012」がウクライナとポーランドで共同開催され、旅行者たちが観戦の「ついで」にチョルノービリ立入制限区域へのツアーに参加しているという情報がありました。このことにヒントを得て、原発事故の起こった土地の未来を学ぶために企画されたのがこの取材です。ロシア語をできる人を探しているということで、わたしが手伝うことになりました。その成果は『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』(2013年)にまとめられています。チョルノービリ区域の観光を扱う本としては先駆的なものでした。
さらにゲンロンは、旅行会社とともに、チョルノービリ立入制限区域への独自のツアーを実施することになり、こちらもわたしが担当しました。そうこうするうちにゲンロンの社員になり、2018年には代表になりました。「チェルノブイリツアー」は2013年から2018年の間に5回実施し、のべ約150人が参加しています。わたし自身はコロナ禍までに取材を含めてチョルノービリに8回行きました。何度も通っているうちに、チョルノービリはわたしにとって「懐かしい」、どこか故郷にも似た場所になっていきました。
2022年になってコロナ禍が収束して、またチョルノービリに行けそうだと思いはじめた頃、ロシア軍がウクライナに侵攻しました。ご存じのとおり、ロシア軍の一部はチョルノービリの立入制限区域を通ってキーウに迫りました。いつも観光バスで通っている道を戦車が埋め尽くす光景や、原発のよく知っている場所に銃を持ったロシアの軍人がいる映像が流れてきたときの衝撃は忘れません。
チョルノービリ原発は、2000年にすべての原子炉が稼働を止めたあとは廃炉作業と配電を行っています。原発ではもともと、ソ連各地から集まってきた技術者たちが働いており、おもにロシア語が使われていました。しかし2014年のクリミア併合とドンバス戦争以降は、次第にウクライナ語が使われるようになっていきます。わたしはロシア語で通訳とコーディネートを行なっていましたが、いつかロシア語では対応できなくなりそうだと感じ、あるときからウクライナの勉強を始めました(まだまだまったくの初学者です)。
ゲンロンではチョルノービリの取材がきっかけで、立入禁止区域の記憶保存活動をしているオレクサンドル・シロタ氏や作家のアンドレイ・クルコフ氏、美術家のアレクサンドル・ロイトブルト氏ら、ウクライナの文化人と交流の機会を持ち、インタビューなども行ってきました。そのうちテクスト化したもののいくつかを「Webゲンロン」で無料公開しています(https://webgenron.com/features/ukraineandrussia)。よろしければ読んでみていただけると幸いです。
考えてみれば、わたしはたまたまロシアとウクライナの両国を年に一度は訪れ、時代の変化や人々の生活、文化のありかたに触れてきました。ふたつの国が戦争をしているいま、どちらとも縁のある者として、できること、やるべきことがあるはずです。今回賞をいただいて、そのような思いを強くしました。
2023年11月、賞をいただいた直後のことですが、戦争開始後はじめてウクライナを訪れました。ポーランドからバスでリヴィウに入り、キーウまでは電車で移動しました。リヴィウはこれが初訪問でしたが、オーストリア=ハンガリー帝国時代の建物が多く残る街並みはキーウなどのこれまで訪れていた街とは異なり、ウクライナ文化の多様さと幅の広さを実感しました。キーウでは、死者を追悼する旗や写真、ロシアからの鹵獲品、それに志願兵募集や軍需品のための寄付を募る広告などを何度も目にして、戦争が日常に入り込んでいるさまを目の当たりにしました。戒厳令で夜が早いこともあり、これまで訪れたときと比べて街に人は少なく、もちろん観光客はおらず、街の活気はリヴィウに比べても控えめで、緊張感があるように感じました。
他方、たとえば空襲警報が鳴っても自分で情報を確認して、本当に脅威があるかどうかを判断し、焦らず日常を送り続けるといった、戦時下を生きる人々の逞しさにも触れました。書店のウクライナ文学コーナーはとても充実しており、戦時下でも新しい詩や散文がたくさん出ていました。2014年以降、ウクライナ語の文学が育っているのが本の数やタイトルから伝わってきます。われわれロシア文学者も、少しずつでもウクライナ語を勉強し、戦争になってしまった国の人々がどのような文化を育み、またロシアに対してどのような感情を抱いているのか、知る努力をするべきだとの思いを新たにしました。かつては「ソ連文化」とひとまとめにされてしまっていたものを丁寧に解きほぐし、別の視点を獲得すれば、ロシア文化に対しても新たな見方ができるようになるのではないでしょうか。
戦争がこの先どうなるのか、両国の社会や市民生活がどう変わるのか、先行きは見えません。戦時下で情報がどのように物語化され、表象されるのか、また、人々が、どのように日々を暮らしているのか、客観的に見て、記録し、評価し、紹介する——わたしたち文学者には重要な役割が課せられているように思います。
いまロシア国内で戦争に反対すると、ロシア軍への名誉毀損として拘束されたり罰金を支払わされたり、ときには過激派に認定され数年間の禁錮刑になることもあります。これを書いているときには、日本文学者でもある作家のボリス・アクーニンがテロリストに認定され、彼の本を出している出版社にも捜査が入りました。かつてはSNSを通して聞こえていたロシアの人々の声は、聞こえにくくなっています。
この戦争をめぐって、インターネットでは戦局やプロパガンダ、ゴシップから誹謗中傷まで、さまざまな情報が飛び交っています。率直な声は聞こえにくくなったとはいえ、混乱した情報のなかに、まだ一人一人の人間の声を聞くことは可能です。こうして、彼らの存在を感じることができるのは救いであるように思います。
戦争という大きなものが人々の生活や運命を左右する時代に、多様で複雑で繊細な方法で表現される人々の声や言葉を扱うわれわれ文学者の役割は重要です。たいへんな時代ですが、頑張って参りましょう。
少しでも早く人々が平和に暮らせる日々が戻ってきますように。