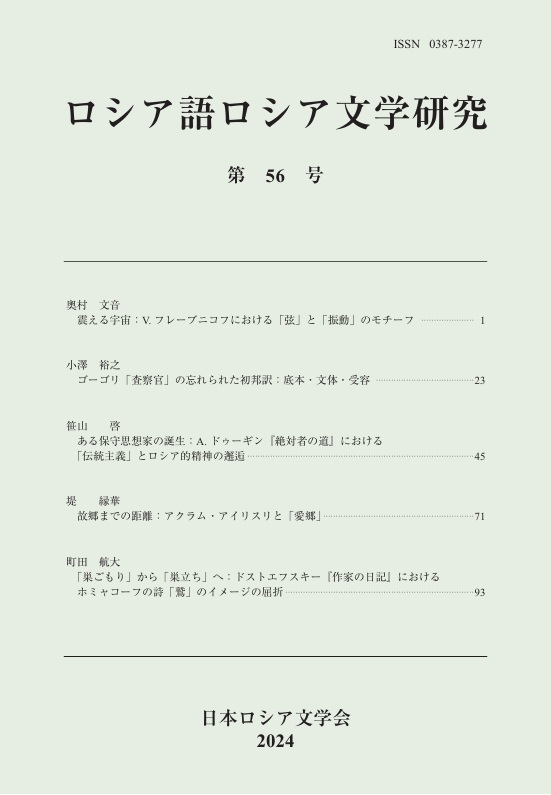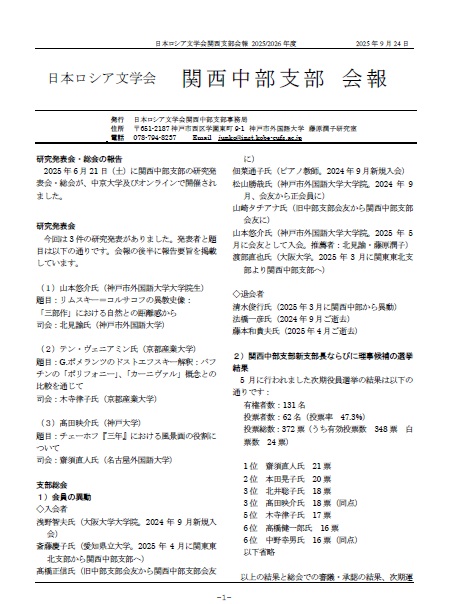木村崇先生の思い出(中村唯史)
木村崇先生は、1944(昭19)年6月、旧満州・黒龍江省のお生まれだから、満80歳に少し満たずに逝かれたことになる。先生から、父親は太平洋戦争末期に戦死、母親は敗戦後に必死の思いで大陸から北海道に引き揚げてきたのだが、小さかった俺を抱えて本当に大変だったんだという話を、何かの折にうかがったことがある。
木村先生は高校までを北海道で過ごした後、本州の大学に入学されるが、まもなく退学して、ソ連のルムンバ民族友好大学に入り直し、68(昭43)年に卒業。帰国後、学生運動が吹き荒れていた71(昭46)年に東京外国語大学の修士課程を修了されている。
雪どけの余韻がまだ残っていた60年代、日本人が高校を卒業後、直接ソ連の大学に入学することが可能な一時期があった。後にこの制度は停止され、89(平成元)年の日ソ政府交換留学制度の開始まで、大学生・院生でもソ連留学が容易ではない時代が続いたのだが、木村先生はこのあいだ、ロシアの言葉と人と社会を実感的・経験的に知悉している数少ない日本人の一人だった。日本の大学を中退してソ連で学ぶ選択をされた理由、青春を過ごされた60年代のモスクワのようすや雰囲気などは、断片的に聞いたことしかなかったのだが、もっときちんとうかがっておくべきだったと悔やまれてならない。
昨年、私の家から電車で10分くらいのところに引っ越して来られたが、数年前から肺を病んで酸素吸入器を常時携帯され、入退院と自宅安静を繰り返されていたためもあって、琵琶湖に面したお宅にうかがえたのは二度だけだった。昨秋京大で開かれたロシア・東欧学会全国大会には、夫人の黒岩幸子先生とともに出席され、車椅子で懇親会にも参加していらっしゃったが、その時の私は開催校の業務でばたばたしていて、きちんとご挨拶もできなかった。車で湖北にある美味しい蕎麦屋にお連れしますと約束していたのだが、それも果たせなかった。
私が木村先生と知り合ったのは、25年ほど前に北海道大学スラブ研究センター(当時)で開催された国際シンポジウムのセッションがきっかけだった。私は報告者の一人で、木村先生はこのセッションの司会だったのである。使用言語はロシア語だった。
木村先生のお名前と風貌は以前から存じ上げていたが、直接お話しする機会はそれまでなかった。大柄で、恰幅が良くて、銀髪はなんだかライオンのようで、身振りやしぐさが大陸的で、やたら声の大きな барин みたいな人がいる……という印象で、当時所属されていた京大では Кимура Грозный の異名を取っているらしいという噂も耳にしていたので、話しかけるのが少し恐かったのでもある。
私たちのセッションは、ロシア文学におけるコーカサス表象が事実上の共通テーマだった。当時はロシア・ソ連を植民地帝国として捉え、オリエンタリズムやポストコロニアリズムの知見をロシア文学の考察にどう生かしていくかが問題となっていたが、ちょうど近代ロシア文学の黎明期に植民地化されたコーカサスの表象は、その焦点となっていたのである。私が報告者となったのは、その数年前のチェチェン紛争時のロシア・ジャーナリズムにおけるコーカサスの表象・定位を分析した論文を書いていたからだった。木村先生は、ルムンバ大学で書かれた卒論テーマはチェルヌイシェフスキーだったそうだが、帰国後にレールモントフに関する論文を多く書かれていたため、司会に選ばれたのだろう。
私たちのセッションは、ロシア連邦軍がチェチェンに侵攻して首都グローズヌイを制圧し、独立派の共和国政府を瓦解させた数か月後という時期に開かれたので、期せずして時事的な緊張感を帯び、センシティヴなものとなった。報告者と司会ということで、前日の懇親会で勇を鼓して挨拶に行ったら、木村先生はすでに激昂していた。私が「チェチェン紛争が…」と言いかけたら、即座に「中村君、これは紛争ではありません、戦争です」と言われたことを今でも強烈に覚えている。
スラ研のシンポは報告ペーパーの事前提出・公開が原則で、私たちのペーパーを木村先生は精読済みだった。幸いというべきか、先生の激昂は私に対するものではなかったが、批判の口調がとても激しかったので、たぶん明日のセッションは嵐になるだろうと覚悟した。
予想通りになった。報告の一つがオリエンタリズム的なコーカサス観を前提としたように聞こえるものだったので、司会の木村先生が流暢だが厳しいロシア語で批判を展開したのである。その報告には私も批判的だったが、その一方で木村先生の反論にも違和感を覚えていた。抽象的な書き方になるが、報告者が抑圧側のコーカサス観を現実・実体として語ったのを、木村先生はやはり現実・実体としての被抑圧側の立場に寄り添って批判したのだけれども、対立する二項のどちらかに共感するという選択では、「抑圧―被抑圧」という二項式を生み出しているメカニズムそのものを批判することはできないと私は感じたのだった。
それで木村先生に対しても批判的な発言をしたのだが、その際に私はどうも「Я категорически против」と口走ったらしい。セッションの終了直後に、友人に「あの表現は、シンポの場では、いくら何でもきつ過ぎる」と注意された。そうかと思ったが、後の祭りだった。
だが、その夜の懇親会で、前日に引き続き勇を鼓して自分の言葉遣いについてお詫びに行ったら、木村先生は覚えていなかった。「そうだっけ? そんなことよりさあ……」と、私のつたないロシア語では理解できなかった発言の趣旨について矢継早に質問を始め、セッションでの議論を再開されたのだった。
その後も何度かセッションをご一緒する機会があったが、木村先生はいつもそうだった。先生にとっては純粋に、議論となっている問題自体が重要で、ご自分が許容できない見解に激昂することはあっても、そこにプライドやら相手に対する感情やらが介入する余地はなかったのである。私は、いつも意見が一致するというわけではなかったが、そういう木村先生を敬愛していた。
この時をきっかけに、私は木村先生が企画されたワークショップに呼ばれたり、共編者をされていた論集に寄稿させていただいたりするようになった。ご一緒した仕事で特に印象深く覚えているのは、2010年秋に、トルストイ没後百周年記念シンポジウムが日本トルストイ協会や日本ロシア文学会の全国大会で開催された際、国際交流委員会の委員長と担当委員として、ロシアや韓国や米国から招聘したゲスト・スピーカーのアテンドをしながら、東京から熊本まで10日間ほど同宿したときのことだ。
木村先生はとにかく好かれ、頼られるのである。某国から招いた一人は新婚で、本国に置いてきた夫人のことが心配で、また端的に寂しくてならなかったようだが、木村先生は、あほらしくて私が逃げていた彼の愁訴にもとことん対応されていた。外国からのお客さまの気分を解きほぐしたり、リクエストに応えて鎌倉に連れて行ったり、秋葉原に案内したりして楽しませることが、木村先生は意識的にではなく自然にお上手だった。人見知りの私でも国際交流で初対面の方々と滑らかに働けたのは、木村先生が委員長だったからこそだと思う。
この時の全国大会では、執行部やゲスト・スピーカーは皆、同じホテルに宿泊していた。韓国からゲストがいらっしゃる日、木村先生と私はこのホテルのロビーで出迎えることになっていたが、国際便の乱れで到着は遅れに遅れた。すでに到着している他のゲスト・スピーカーの方々の歓迎会がホテルのレストランで始まったが、木村先生は断固として「国際交流担当者が、外国からのお客さんを、赤い顔で出迎えるわけにはいかない」とおっしゃった。私は飲み会いいなあ、早く合流したいなあ、合流してもいいんじゃないかなあとひそかに思ったし、木村先生も「中村君は委員長じゃないんだから、飲んでいても良いよ」と言ってくださったけど、やはりそういうわけにもいかず、私たちはコーヒーだけでロビーに座り続けたのである。
結局、韓国からのゲストがホテルに着いたのは午後10時近かった。それからそのかたも交えて、さらに午前1時過ぎまで歓迎会が続いたが、木村先生は翌朝早くから颯爽と会場に姿を現した。ゲストの一人から、賞賛とも皮肉ともなく、「日本のロシア文学者はロシア人より飲みますね」と言われると、木村先生は言下に「もちろんです、ロシア文学を理解するために必要なことです」と応答されていた。本気だったのか、冗談のつもりだったのかはわからない。
木村先生は、豪放磊落な自由人のように見えたし、実際そうであったとも思うが、一面ではとても感覚が鋭く、繊細なかたでもあった。「なぜレールモントフを専門にされたんですか」と聞いたら、「詩の響きが良いからだ」と即座に回答されたことがある。昨年5月に琵琶湖畔の新居にうかがった際には、リビングの広い窓から湖面を眼下に見ることができたが、「琵琶湖は毎日色が違うんだよね。同じ日でもどんどん変わっていく。何時間でも見ていられるね」とおっしゃっていた。
鋭敏な感覚と我執のない精神で、いま取り組むべきと判断した問題に次々と真正面からぶつかっていくのが木村先生の生き方で、方法論とか(酒席で昔、私を「二項式の鬼」と呼んだのは木村先生で、このことだけは今でもちょっと根に持っている)、ご自分の研究をまとめるというようなことは、おそらく考えてもみなかったんじゃないかと思う。そんな木村先生が残された言葉で私が一番印象深く覚えているのは、ある文章中の「自分の父親は犬死にだった。戦争は多くの人を犬死にさせる。自分はだから反戦平和の立場に立つ」という趣旨のものだ。こういう実感に根ざした断言がいかにも木村先生らしいが、これよりも確かな反戦平和の根拠を私は知らない。
私が知る木村先生は、初めて言葉を交わしたときからずっと、酸素吸入器を装着して呼吸が苦しそうになってからも、いつもご自分が間違っていると思うものに激昂し、軒高とした口調の明確な言葉で、激しくこれを批判しておられた。そんな木村先生がいま私たちと一緒にいないというのは、なんというか、らしくないのである。存在感の塊のようなかただから、偲ぼうにもいまだに実感がない。木村先生がまた学会や研究会やシンポにお洒落な服装で大柄な姿を現し、挙手より早く大声で発言を始められるような気がしてしかたがない。
中村唯史