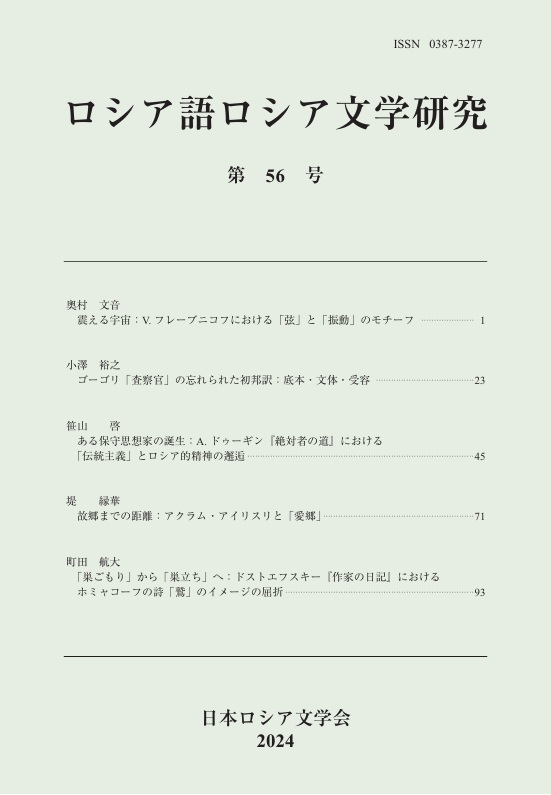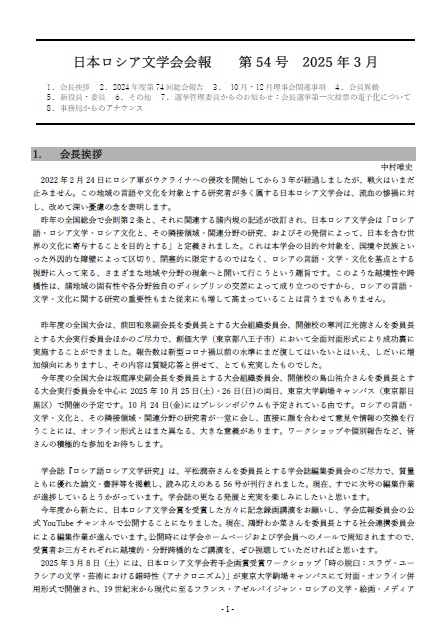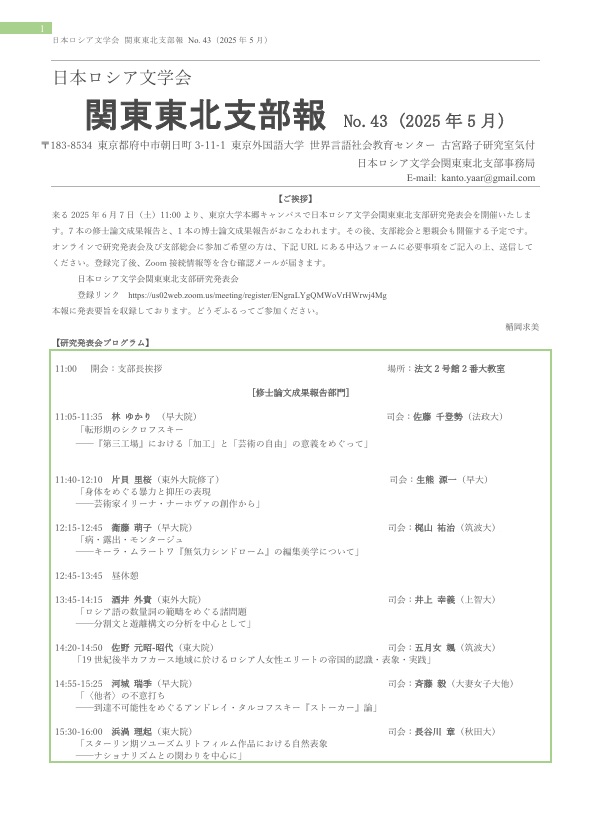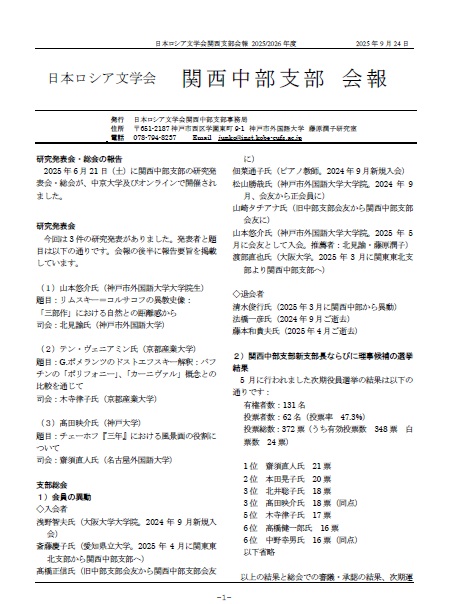井桁貞義先生の思い出
高柳聡子
2024年8月22日に井桁貞義先生が旅立たれた。
私がご逝去の報に触れたのは、約一か月後の9月26日だった。亡くなられたことについては大々的な告知などをせず、自然と伝わっていくことをご遺族が望まれていると聞いた。井桁先生ご自身のご希望でもあったのだろうか、とても先生らしいと思った。
井桁先生の業績と功績については、私がここで繰り返すまでもなく、より詳しくご存じの方が多くいらっしゃることと思う。2013年に先生が早稲田大学を退職される際に、「井桁先生を送る会」で配布するための業績表をゼミ生で作成したところ、それは、A4で17頁にわたるものになった。現在はもちろん、そこにその後の10年分のお仕事を加えなければならない。驚嘆する点はいくつもある――学部時代からロシア文学・文化に関する同人誌などを精力的に作っていらっしゃること(もし先生が21世紀の学生だったなら楽しそうにZINEを作って文フリあたりに出ていたのかもしれない)、修士課程のあいだにも論文を複数書かれていること、にもかかわらず、後に単著となるレベルの修士論文を執筆されていること(『私・他者・世界:ドストエフスキイにおける〈意識〉の問題』(清信社、1972年)等々である。これまでの業績を俯瞰するだけで、研究者としての問題意識の核が明確にあり、すべての関心はそこから放射線状に延びていたことがよくわかる。
井桁先生は新しいものがとても好きだった(これは誰もが知っている)。先生の中では、「いま」とその先に続く「未来」が常に可視化されていたように思う。とても解像度の高い感性とまなざしをお持ちだった。1970年代に研究者として歩みはじめた先生にとって、来たる世紀末と新世紀を見据えた世界には、見逃すことのできない新しいものが溢れていたに違いない。2001年に大学院に入ったというのに、ぼんやりと自分の手元だけを見ていた私には、なんだか超人のように映った。文学というのは地味で陰気で孤独な行為だと思っていたのに、その地味さも陰気さも孤独もなにひとつ手放さずに、地下室人のままで「ロシア文学と現代」を鮮やかに語る存在は前衛的ですらあった。
そんな先生の講義やゼミは早稲田大学では絶大な人気を誇っていた。私も学部時代は、大教室の片隅でマイクを通した先生の声を聴くことしか叶わなかったが、大学院で井桁ゼミ生になってからは言葉では言い表せないほどお世話になることになる。井桁ゼミは毎週金曜日の5-6限にあり、院生が2名ずつ発表を行う。矛盾した言い方になるかもしれないが、井桁先生は非常に理性的だけれど、感情を偽らない人でもあった。時には、きちんと話を聞こうとしないゼミ生に対して苛ついたり、怒鳴りつけたりすることもある。不快に感じたことも率直に言葉にする。だから私は先生の顔色を窺う必要もなく、安心してついていけた。写真に残っている先生の笑顔は、どれも心からのものなのだとわかる。金曜の夕刻のゼミは楽しく、実り多いものだったから、私は博士課程を終え、教えるようになってからも、先生が引退されるまでずっとゼミに出続けてしまった。
実のところ、研究者を育てるということに関して、先生は一切の手抜きをしなかった。あのゼミでなければ、自分が博論を書けたかどうか自信がない。正直に言うと、ひとつひとつの論文や発表を毎回事前に見ていただき、先生の多大な時間と労力を奪ってしまったことを申し訳なく思う自分もいる。それでも、博論を書き終わり、露文コースの助教になったときに、これまでのご指導へのお礼を伝えると、先生はいつものあの軽い感じで「僕はなんにもやってないよー」と楽しそうに笑っていらした。
自分が主役になるべきときには見事に役割を果し、そうでないときはアシストにも裏方にもなる――そんなふうにして、ゼミが、コースが、大学が、学会が、世界がうまくまわることに尽くすという姿勢を、私は先生の生き方から学んだ。私が役立てる場所は比較にならないほど少ないけれど、こうして先生の記憶をたどっていると、まだまだ頑張らなければならないし、頑張っていけるという気がしてくる。
晩年は闘病生活でご苦労されたことと思うが、2023年に私が訳書を出すことを報告した際には、「これからはライバルだね」という言葉をくださった。この他愛のない一言に、私がどれだけ強い緊張を覚えたか、先生はご存じないだろう。もちろん、私が先生のライバルになどなれるわけもない。古今東西の文学・哲学から最新の文学、ネット事情まで無敵の教養に支えられた先生は、これからも私にとって尊敬する指導教授のままだ。そして、私がもっとも信頼するドストエフスキイ研究者である。
先生、長いあいだ本当にありがとうございました。先生がいない世界に私たちはまだ慣れることができません。これからも時には金曜の夜に集まって、早稲田や吉祥寺で一緒に過ごしたあのゼミの日々を思い出すことでしょう。「研究者として悔いのない人生を」――いつかいただいた言葉は常に胸にあります。どうぞ、まずはゆっくりと休息なさってください、それからまた、いつか書きたいと仰っていたご著書に取り組まれてください。